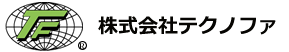044-246-0910
ISOの各種マネジメントシステム規格では内部監査を行うことを必須事項として求めています。ISOマネジメントシステムの有効活用の上では、第三者審査よりも内部監査の方がより重要と考えるからです。第三者審査はどうしてもお金がかかることから掛ける工数には限りがあります。その点、内部監査にはその制約はありません。もちろん内部人材の活用とは言え、そこには内部コストが発生しますから、無料で内部監査が実施できるわけではありません。ですが、組織の状況にもよりますが、第三者審査において審査員が使う工数の2倍も3倍もの工数を内部監査にかけることは可能です。それによってより広く、深く組織の状態を確認することができるようになります。
さて、ではその内部監査を行う内部監査員とはどのような人がなればよいのでしょうか。そして時々頂戴する質問として、内部監査員資格というものはあるのでしょうか、ということも含めて解説していきます。
まずISOの構築、運用において内部監査員の任命は必要ですが、そこに内部監査員資格が必要かというと不要、という答えになります。あくまで社内で内部監査員を正式任命していただければよいのです。それを社内資格と呼ぶ場合もありますので、その呼称を組織内で使う分には全く問題ありません。しかし再確認ですが、内部監査員になる為に何か資格を取らなければいけない、という仕組み、決まりは全くありません。では内部監査員になる為に研修を受講しなければいけないか、と言うご質問が更にあったと考えると、この答も不要です、となります。
組織で内部監査を行う上で必要と考える力量設定を行い、その力量があると評価判定をした人が内部監査を行うことで、規格対応上は問題ありません。但し有効性ということを考えると、その内部監査員が実施した内部監査が効果的であったかどうかはマネジメントレビューでチェックしたり、第三者審査において審査員から審査を受けるということにはなります。そこであまりリスクを負いたくないと考える組織は、外部の内部監査員養成研修を受講し、その合格証でもって社内基準をクリアしたと判断して内部監査員任命を行っている組織もあります。このやり方で必要条件は満たしますが、十分条件を満たすかどうかは冷静、客観的な評価が望まれるところです。
また、内部監査員を一度任命した後、継続任命する場合の仕組みも考えていただきたい部分になります。組織の中での仕組みや取り扱い商品が変わった場合の対処をどうするのか、また、ISO規格が改訂になった場合の対応はどうするのか、要員の力量維持そして強化もISO規格上は明確に規定される部分ではなく、組織の判断に任せられています。よって内部監査員にも実は相当な力量のバラつきが生じてしまっているのが実態です。必要な教育の時間と予算の確保をしっかり行い、有効な内部監査の実施につなげるようにしましょう。