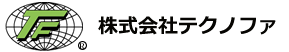044-246-0910
ISO審査員が知っていると有益な情報をお伝えします。
トランプ大統領の登場で今後の日本経済の動向は多くの人の興味のあるところです。世界の自由経済社会の混乱がある期間続くにしても、より高い製品開発能力を獲得し、製品の付加価値を高めることは資源のない日本社会の宿命です。世界のサプライチェーンが大きく変わるかもしれないこの先数年の動きは注意深く観察されるべきことですが、日本国内のサプライチェーンを担う物流の効率化も避けては通れない大きな課題です。
■物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化
総合物流施策の柱として、「物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化」が掲げられます。これまで生産性向上等の観点からその必要性が認識されながらもなかなか進捗してきませんでした。物流の機械化やデジタル化、そしてそれらの前提となる伝票やデータ、外装やパレット等、物流を構成する各種要素の標準化の推進を通じて物流分野におけるデジタル・トランスフォーメーション(物流 DX)の実現は地味ではありますが、物流の足腰を強くする大切な活動です。
■時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流構造改革の推進
次の柱は「労働力不足対策と物流構造改革の推進」です。生産年齢人口の減少や、トラックドライバーへの時間外労働の上限規制の適用を踏まえ、トラックドライバーや船員の働き方改革や、労働生産性の改善に向けた革新的な取組みの推進等を図っていくことが必要です。物流分野における働き方改革少子高齢化や人口減少を背景として、物流分野においても、特にトラック業界、内航海運業界を中心として高齢化が進んでおり、大量退職や、生産年齢人口の減少に伴う人材確保が困難になることへの対応が引き続き必要となっています。
人口減少に伴う労働力不足に加え、トラックドライバーの時間外労働時間規制、カーボンニュートラル、燃料高・物価高への対応として、令和5年の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」による最終とりまとめや、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」で提案されている「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づき、抜本的・総合的な対策に取り組んでいかなければなりません。
トラック運送事業においては、平成30年12月に成立した改正「貨物自動車運送事業法」に基づき、「標準的な運賃」の浸透を図るなど各種施策に取り組むとともに、賃上げ原資となる適正運賃の収受に向け 「標準的な運賃」の見直しが行なわれ、「自動運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」に基づいた物流の効率化、取引環境の適正化等が推進されてきました。
休憩施設の駐車マス不足解消や使いやすさの改善に向けた取組みとして、令和5年には高速道路機構及び高速道路会社が取りまとめた整備方針により、休憩施設の駐車マス数の拡充等の対策が取られています。
物流分野における労働力不足、多頻度小口輸送の進展等に対応し、物流事業の省力化及び環境負荷低減を推進するため、関係者が連携した物流の総合化・効率化に関する幅広い取組みを支援することを旨とした「物流総合効率化法」 が作成され、共同輸配送、モーダルシフト、輸送網の集約等を内容とする総合効率化計画が約400件を認定され、運行経費等補助や税制特例措置等の支援が実施されてきました。 令和5年には「物流革新緊急パッケージ」において、鉄道(コンテナ貨物)、内航(フェリー・RORO船等)の輸送量・輸送分担率を今後10年で倍増させることが申し合わされました。設備類の標準化については、令和3年から開催している「官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会」 が作られ、標準的なパレットの規格と運用やその推進方策について議論を行われました。物流データの標準形式を定めた「物流情報標準ガイ ドライン」の活用促進を図るため、「物流情報標準ガイドライン利用手引き」も作成され周知がされました。
■地域間物流の効率化
複合一貫輸送等の推進に向け、港湾・貨物駅等の物流結節点の整備等が進められています。貨物鉄 道輸送については、他の輸送モードとの連携 (モーダルミックス)が不可避であり、誰でもいつでも利用できる体制づくり、貨物駅の高度利用、貨物鉄道のスマート化の推進等を促進していくこととされています。
路上荷さばき駐車を削減するため、駐車場法に基づく駐車場附置義務条例に荷さばき駐車施設を位置付けるよう地方公共団体に要請がされています。令和5年現在で、89都市において、 一定規模以上の商業施設等への荷さばき駐車施設の設置を義務付ける条例が適用されている状況になっています。
トラックドライバー不足が深刻化する中、配達の削減に向けては、令和5年の国土交通省会議で決定した「物流革新緊急パッケー ジ」を受け、消費者が再配達削減に取り組むよう促すため、宅配便やEコマースの注文時に、コンビニ受取等、物流負荷軽減に資する受取方法等を選択した場合に、消費者にポイントが還元される仕組みを社会実装すべく、実証事業を実施する政策が実行されています。
無人航空機(いわゆるドローン等)は、離島や山間部等における物流網の維持や買い物にける不便を解消するなど、地域課題の解決手段として期待されている。令和2年度には「過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業」を創設し、5年度までの4か年において、全国63地域の事業を採択するとともに、 「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」において、レベル4飛行によるドローン物流等の先進的な実証事業を9件採択 し、実証事業を行った。また、2023年3月に公表した「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.4.0」も活用しながらドローン物流の社会実装を推進した。
国土交通省 令和6年版 国土交通白書
■強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築
3つ目の柱は「強靱で持続可能な物流ネットワークの構築」です。昨今激甚化・頻発化してい地震、洪水、さらには本年頻発した山火事などによるサプライチェーンの途絶等を踏まえ、物流ネットワークの強靱性・持続可能性の確保を喫緊の課題としてとらえて、我が国産業の国際競争力強化等に資する物流ネットワークの構築のほか、脱炭素社会の実現という目標達成に向けた取組みを推進することとされています。
国内輸送の約9割を担う貨物自動車による輸送における効率的な物流ネットワークの構築は 極めて重要であり、三大都市圏環状道路や空港・港湾へのアクセス道路等の整備を進めている。平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な路輸送網を「重要物流道路」として指定し、トラックの大型化に対応した道路構造の強化や災害時の道路の啓開・復旧の迅速化等の機能強化 及び重点支援を実施している。令和4年4月1日からは、調査中、事業中区間を重要物流道路に追加指定し、4年7月1日には、重要物流道路のうち国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行に道路構造等の観点から支障のない区間を、特車許可不要区間として追加指定した。
また、車両運行管理支援サービス等の、 ETC2.0を活用した取組みを推進しているほか、令和2年5月27日に公布された改正「道路法」により創設された特殊車両通行確認制度を4年4月1日に運用を開始した。また、道路情報の電子化の多頻度化、特に利用が多い経路 の国による道路情報の電子化の代行、確認システム利用マニュアルの作成等の確認制度の利用促進を行った。
さらに、複数のドライバーが長い輸送行程を分担することで日帰り運行を実現する「中継輸 送」の拠点として、令和6年4月には、「コネクトパーキング岡山・早島」を新規事業化した。 トラック輸送の省人化を促進し、生産性向上を図るため、一台で大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」を平成31年1月より本格導入し、令和4年11月には、事業者の要望を踏まえ、更なる対象路線の拡充を行った。引き続き、利用促進を進める。加えて、高速道路と民間施設を直結する民間施設直結スマートIC制度の活用を推進するとともに、引き続き、スマートICの整備を進めるなど、既存の道路ネットワークの有効活用・ 機能強化を図っていく。国土交通省 令和6年版 国土交通白書
(つづく)Y.H